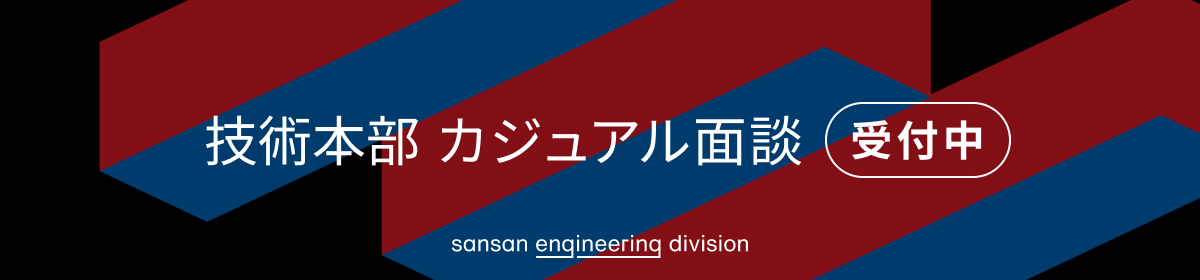生成AI技術の飛躍的な進歩により、ソフトウェア開発にAIツールを活用することが一般的になりつつあります。そして、Sansan株式会社は社員一人ひとりがAIを武器として活用できる状態を目指す「AIファースト」を、2025年の全社方針として掲げています。
この変革の波は、QA組織にも根本的な変化をもたらしています。従来のテスト手法やプロセスが、AI活用により劇的に効率化される一方で、QAエンジニアの役割そのものが進化を求められる時代が到来しました。
Quality Assurance Engineering Unit部長の佐藤です。私は2023年11月にSansanへ入社し、2025年3月に部長へ就任してQA組織の体制変更と変革をリードする立場になりました。今回は、これまでの経験と現状を踏まえ、AI時代に向けてQA組織をどう変えていきたいかという私の考えについて語りたいと思います。
1. QA組織の現状と変革への道のり
私がSansanに入社した当初から、この会社では「品質」を単に機能が仕様通り動作することだけでなく、顧客に真の価値を届けることと捉えていました。この広義の品質への取り組みを通じて、QA組織のスコープを拡張していく方針が示されていたのです。
入社時はQAエンジニアとして、Sansanプロダクトのデータ分析に着手し、データドリブンな開発推進に取り組みました。同時にQA組織の業務改善を推進する戦略チームにも参加し、組織課題の深層を理解していきました。
この経験を通じて気づいたのは、Sansanが成長していく上で「品質保証のあり方」そのものが重要な課題であるということでした。手法やプロセスだけでなく、それを担う組織の構成、ケーパビリティ、文化といったQA組織全体のあり方を変えていく必要性を強く感じるようになりました。
2. 従来型QAからの脱却とシフトレフト
従来のSansanのQA体制は、開発の後工程で品質を確認するスタイルが中心でした。開発チームから依頼されたテスト案件を実行し、リリース前の回帰テスト(リグレッションテスト)を行うという、受動的なやり取りが主流だったのです。
しかし、この手法には限界がありました。問題が発見された時の修正コストが高く、QAエンジニア自身もプロダクトに対する当事者意識を持ちにくい構造になっていたのです。
そこで推進したのが、QAエンジニアがプロダクトの企画段階から参加する上流工程からのQA関与への転換でした。企画の初期段階からユーザー視点での品質観点を提供し、開発プロセス全体を通じて継続的に品質を監視・改善するモデルです。
これは単に上流の修正コストが安い段階で問題を解決するだけでなく、QAエンジニアがプロダクトに対してオーナーシップを持つこと、キャリア形成、やりがいといったさまざまな観点からも重要だと考えています。特に、作っている製品が提供しようとしている顧客価値と戦略を理解し、その実現に深く関わることは、QAエンジニアのキャリアにとって非常に重要な要素です。
品質保証には、仕様に対する検証(Verification:正しく作れているか)と、そもそも正しいものを作っているかの確認(Validation:正しいものを作っているか)の両面があります。後述しますが、AI活用の進展により、Verificationの多くはAIによって担える可能性が高く、人間はValidationにより集中するという比重の変化が起きると考えています。
このような上流工程からのQA関与への移行を進めているところですが、シフトレフトへの改革はまだ始まったばかりです。各プロダクトで状況が異なり、リソースも限られている中で、四半期ごとに目標を立て、PdMや開発チームとの関わり方を変える施策を試行錯誤しながら着実に進めています。
3. AIファーストがもたらす変革の必要性
そうした中で、新たな変革の波が押し寄せてきました。Sansan全社が掲げる「AIファースト」です。開発チームでもDevin、Cursor、Claude CodeなどさまざまなAI支援ツールを積極的に活用し、効果的な活用方法を模索しています。
AIによるコーディング支援により、開発の効率と速度が飛躍的に向上する一方で、QA側が従来のアプローチにとどまることは現実的ではありません。開発プロセス自体の根本的変化に対応するため、QA組織もまた根本的な改革が必要な状況です。そして、このAI活用こそが、前述したシフトレフトへの改革を加速させる鍵になると期待しています。
現在、QA組織では業界で実践が始まっているAI活用アプローチを採用し、検証を進めています。これは大きく2つの分野に分かれます。
テスト業務の効率化
- テスト計画・設計・ケース作成:要件定義書や仕様書を基に、AIがテスト設計とテストケース作成を支援
- テスト自動化:PlaywrightテストのAI生成
業務プロセスの効率化
- 情報収集・要約:社内のあらゆるデータソース(Slack、Notion、Google Driveなど)から情報を収集・加工・要約
- ドキュメント生成:目標設定、成果報告、共有資料など業務に関わるドキュメントの作成支援
- データ可視化:QA業務に関するデータの収集と分析用スクリプトの生成
これらの取り組みにより、従来人手で時間をかけていた作業を効率化し、より戦略的な品質保証に注力できる環境を構築しています。
4. 統合されたAI活用ワークフローの構築
現在のトライアル段階では、人間が必要な情報を収集し、細かい指示を含んだプロンプトを手動で作成し、出力を確認・修正するという工程を繰り返しています。これらの個別の取り組みから得られた知見を生かし、次のステップとして各プロセスをより効率的で実用性の高いワークフローに発展させていきたいと考えています。
我々が構築を目指しているのは、テスト計画からテスト自動化まで、各工程において冗長な入力を最小化し、ユーザーが簡単に実行と結果検証を行えるワークフローです。
具体的には、対象プロダクトやPBI(Product Backlog Item)のIDなど、ワークフローに応じた最低限の情報を専用インターフェースで選択・入力するだけで、システムが自動的に関連情報を収集します。要件定義書、システム設計書、既存機能の仕様、コードベース、利用統計データなどから、リスク分析、テスト設計、テストケース作成、テスト自動化コードの生成まで、一連の流れをパイプライン化して実行できる仕組みを想定しています。結果は事前に決められた場所へ自動的に出力され、QAエンジニアはそれを確認・検証するだけで済むようになります。
重要なのは、これらのツール群をただ連携させるだけでなく、次の要素を確実に実現することだと思います。
透明性の確保:AIがどの資料を参照してどういう戦略とロジックで最終アウトプットに至ったのかを簡単に理解できるトレーサビリティを提供します。これにより、QAエンジニアは効率的にレビューでき、必要に応じて戦略を調整できます。
バージョン管理とガバナンス:プロンプトを含むロジックの変更履歴を適切にバージョン管理し、品質向上の取り組みを継続的に改善できる体制を構築します。異なるプロダクトやチームでの知見共有も、この仕組みを通じて実現していきます。
AI活用を前提とした成果物の整備:AI活用に必要な要件定義書などの開発成果物が適切に整備されていることが前提となります。これはQAエンジニアに限らず、PdM、デザイナー、開発エンジニアなど、すべてのロールにおいてAIを前提とした開発プロセスに移行するために重要な要素です。アジャイルに動きながらも、AIが効果的に活用できる形での必要なドキュメンテーションや成果物の作成を、組織全体で意識していく必要があります。
段階的な導入と検証:各プロダクトの特性に応じて段階的にワークフローを導入し、効果を検証しながら最適化を重ねていきます。
このようなワークフロー基盤により、QAエンジニアは定型的な作業から解放され、より戦略的で価値の高い品質保証活動に集中できるようになります。
5. AI時代のQAエンジニアの役割進化
AIの活用は単なる効率化にとどまらず、QAエンジニアの役割そのものを変えつつあります。
AIによる業務変化と新たな価値領域 前述したように、従来の定型的な作業の多くがAIによって自動化される一方で、次のような領域では人間のQAエンジニアの価値がより重要になります。
- AI出力の検証・妥当性確認:AIが生成した結果を品質基準やビジネス要件に照らして評価する
- 品質戦略の立案:リスクが集中する領域を見極め、限られたリソースを最適に配分する
- 上流工程での品質設計(Validation):PBIの課題設定が本質的か、提案されているソリューションが真に顧客価値を生み出すかといった評価
- AIワークフローの設計と業務領域の拡大:AIの活用方法や業務プロセスへの統合といった構造設計に加え、データ分析を用いた内部品質と外部品質の検証、価値の定義と測定など、従来データアナリストが担っていた領域もQAの管轄として取り組む
このように、AI活用によってQA組織の業務領域は大幅に拡大し、各領域のスペシャリストを目指すことで、QAエンジニアのキャリアパスの多様化が実現されます。従来のテスト実行中心の業務から、より戦略的で価値創出に直結する品質保証業務への転換が進むでしょう。
変化への適応能力の重要性 これはQA組織やQAエンジニアに限ったことではありませんが、AI時代では何より柔軟性と適応能力がスキルとして今まで以上に重要になると考えています。改革と変化を恐れず最高なプロダクトをスピード感をもって世の中に提供し続けるには、あらゆる変化に対応していくことを当たり前と受け入れ、ハイペースな変化を楽しめることも重要な要素になるでしょう。
6. QAの未来を共に創る
SansanのQA組織は今、AIを活用しながら次のステージに進もうとしています。これは単なるツール導入ではなく、組織文化やエンジニアの役割そのものを変革する挑戦です。
この変革は、QA業界全体にとっても重要な意味を持つと考えています。AIによって定型的な作業が自動化される一方で、より戦略的で創造的な品質保証活動に集中できる環境が生まれます。QAエンジニアの専門性と価値がより明確になり、ソフトウェア開発における存在感がさらに高まるでしょう。
SansanのQA組織で実現できること
- 変革の最前線での経験:AI活用によるQA業務の根本的変革に、設計段階から参画できます
- 多様なキャリアパス:テスト専門家、品質戦略家、データアナリスト、AIワークフロー設計者など、さまざまな専門性を追求できます
- プロダクト価値への直接貢献:Sansanの「ビジネスインフラになる」というビジョンの実現に、品質面から貢献できます
- 組織文化の創造:新しいQA組織の文化とプロセスを、メンバー全員で創り上げていけます
品質保証に関心を持つ方にとって、今は非常に興味深いタイミングです。新しいテクノロジーを活用しながら、QAの未来を形作っていく絶好の機会だと思います。
変化を楽しみ、新しい挑戦に前向きに取り組める方と、一緒にQAの未来を創っていければと思います。
Sansan技術本部ではカジュアル面談を実施しています
Sansan技術本部では中途の方向けにカジュアル面談を実施しています。Sansan技術本部での働き方、仕事の魅力について、現役エンジニアの視点からお話しします。「実際に働く人の話を直接聞きたい」「どんな人が働いているのかを事前に知っておきたい」とお考えの方は、ぜひエントリーをご検討ください。