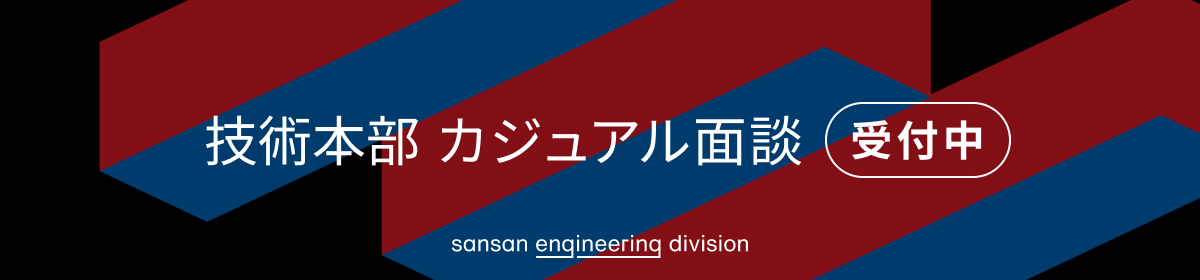こんにちは。SansanのVPoE、大西です。
先日、Sansan技術本部で、全エンジニアが集まる半期総会が開催されました。今回のテーマは「AI時代の挑戦型組織へ」。私はこの場で、Sansanエンジニアリングの現在地と、これからの進化の方向について語りました。
こんにちは。SansanのVPoE、大西です。
先日、Sansan技術本部で、全エンジニアが集まる半期総会が開催されました。今回のテーマは「AI時代の挑戦型組織へ」。私はこの場で、Sansanエンジニアリングの現在地と、これからの進化の方向について語りました。
本記事では、総会で私が伝えたかったメッセージを改めてまとめています。Sansanがいま、どのような組織文化と人材を求めているのか。そして、AI時代におけるエンジニアリングの価値をどのように再定義していこうとしているのか。その輪郭を、少しでも感じていただけたら嬉しいです。
なぜ今、「挑戦型組織」への変革が必要なのか?
私たちを取り巻くビジネス環境、そして技術トレンド、特に生成AIの進化は、かつてないスピードで変化しています。この変化は単なるツールの進化にとどまらず、プロダクト開発のあり方、私たちの働き方、そしてビジネスモデルそのものに「非連続な変化」を迫っています。
これまでSansanは、マネジャーが主導し、日々の業務の効率化や既存プロダクトの着実な改善を通じて、素晴らしい「連続的な成長」を遂げてきました。これは私たちの揺るぎない強みであり、これからも変わらない重要な役割です。しかし、このAIが加速させる市場競争において、既存の枠を超えた新たな価値創造なしに、Sansanの次なる飛躍はありません。変化の速度は増し、既存の延長線上にある思考だけでは限界があります。
だからこそ、私たちは今、「リーダー」の存在を強く求めています。ここでいうリーダーとは、特定の役職者に限られるものではありません。全エンジニア一人ひとりが、自らの持ち場で「非連続な成長」を牽引するリーダーシップを発揮する行動を指します。現状の枠を超えた新しい価値の創造、未踏の領域への挑戦、そして組織全体を巻き込む変革を恐れずに推し進める。これこそが、AI時代のSansanに不可欠な「挑戦型組織」の姿です。つまり、これからのSansanは『マネジャー型』から『リーダー型』へ、管理型から挑戦型の組織へ進化していきます。
AIネイティブなSansanを創る:AIとの「共同知能」
「挑戦型組織」への変革の中核となるのが、AIネイティブな組織への進化です。私たちは、AIを単なる便利なツールとして使うだけでなく、Sansanのプロダクト、サービス、そして開発プロセスの中核に据え、AIと共に新たな価値を創造する集団を目指します。
AIネイティブな組織とは、単に「AIで何ができるか」を探すだけでなく、「自分たちの仕事やプロダクトをAIでどう変えられるか」を問い続け、実行していくことです。 私たちエンジニアは、単に「技術をどう使うか」を考えるだけでなく、「その技術で何を変えたいか」を語れる存在でなければなりません。PdM(プロダクトマネジャー)に任せきりにするのではなく、エンジニア自身がプロダクトや顧客価値に深くコミットし、AIを駆使して未来を創造していく。その視点を持つことが、AI時代の挑戦型組織に不可欠です。
この「AIネイティブ」な組織を築き、AIとの「共同知能」を実践するための主要なガイダンスとして、AI実用研究の第一人者であるイーサン・モリック氏の著書『これからのAI、正しい付き合い方と使い方 「共同知能」と共生するためのヒント』で提唱する以下の4つの原則をSansanのエンジニアリング部門内で共有しています。
常にAIを参加させる: あらゆるタスクや問題解決の最初から、AIをデフォルトのパートナーとして考慮し、積極的に試行錯誤を通じて活用します。倫理的・法的に問題がない限り、あらゆる仕事でAIに助けを求め、特定の状況下でのその能力と限界を発見していくことが重要です。
人間参加型にする: AIだけに任せるのではなく、人間が常に最終判断を下す仕組みを維持することです。AIはハルシネーション(幻覚)や嘘をつくことがあり、批判的思考と監視が不可欠です。AIの出力の真偽を見抜ける基礎的な知識と、人間の専門知識が不可欠な場面を見極める「AIリテラシー」を向上させます。
AIを人間のように扱う(ただし、どんな人間かを伝えておく): AIに明確なペルソナを与えることで、より的確な結果を引き出す「プロンプトエンジニアリング」を磨きます。ただし、AIに意識や自我はないことを決して忘れず、過度な擬人化は避けるべきです。
「今使っているAIは、今後使用するどのAIよりも劣悪だ」と仮定する: AI開発の指数関数的な進化を認識し、現状に満足せず、常に未来の改善・進化を念頭に置き、継続的な学習と適応、そして将来性保証への積極的な投資を行います。
これらの原則に基づき、私たちはこれからの3ヶ月で、具体的な挑戦目標を設定しています。
各部でAIネイティブな組織への変革ロードマップを作成し、社内公開すること。
各プロダクト部門でAIを全開発プロセス(企画、設計、実装、検証)に組み込んだPBI(プロダクトバックログアイテム)を1件以上リリースすること。
部長・GrMなど役職者も、AIを活用した開発を経験すること。
これらの目標は、AIネイティブな組織へと変革するための具体的な第一歩であり、全員が当事者意識を持って挑戦していくことを期待しています。
AI時代に進化するエンジニアの本質的な価値
AIの進化は、私たちエンジニアの役割そのものに大きな変化を促します。 もしかしたら、これまで「エンジニアの醍醐味」と感じてきた「コードを自分で書く」という作業の比重は減っていくかもしれません。しかし、これは決してエンジニアの価値が下がることを意味しません。むしろ、AIに定型的な作業を任せることで、私たちはより高次元で、人間にしかできない価値創造に集中できるのです。
そのためには、いくつかの「アンラーン(学びほぐし)」が必要です。
「コードを書く=価値創出」という固定観念: 「実装量」や「複雑なコード」が評価される時代は終わり、これからは「課題を定義すること、AIを活かす構造を設計すること」に価値を移します。
「自分の手でやらないと意味がない」という思い込み: 「自分が理解して実装したものが一番安心」という考えから、AIによる生成物を理解し、意図をもって選択・検証できることが重要になります。「AIと共創する」ことへとシフトします。
「正解のある世界での最適化志向」: これまでは仕様が決まっていて、それをいかに速く・正確に実装するかが問われた時代でした。しかしこれからの仕様や課題が流動的なAI時代では、私たち自身が「問いを設定する」側に回る必要があります。「How」を考える前に「WhyとWhatを探求する」姿勢へ転換します。
「知識=差別化」の幻想: 自分だけが知っている技術や手法が強みだった時代から、知識やノウハウはAIによって瞬時に平準化される時代になります。「知識を活用する力・構造化する力・共有する力」が真の強みとなります。
では、私たちがアンラーンすべきことを踏まえ、AIネイティブな時代に、エンジニアとしてどのような本質的な価値を磨いていくべきでしょうか? 私は以下の5つの力を特に重要だと考えています。
問題を定義する力: 技術の力で何を解決すべきかを言語化・構造化できる力。良い問いなしに、AIをどう使っても価値は生まれません。
構造設計・ワークフロー設計能力: AIを単に使うだけでなく、人、AI、そして既存のシステムが連携する最適なワークフローを設計する力。特に、ソフトウェア開発プロセスそのものを「AIファースト」に設計し直せる人材は、この時代に非常に貴重です。
コラボレーションと知識流通力: AIが生成する知識を、チーム・組織全体に流通させ、再利用可能にする設計力。自分の仕事が「他の誰かの学習素材になる」よう意識できる人は、組織全体の知の進化を加速させます。
スピードと打席数の最大化: AIによって試行錯誤のサイクルは劇的に高速化します。この速度を最大限に活かし、フィードバックを自動で得る環境を整えられる人。数多く試し、早く学習し、価値あるものに集中するスキルが、AI時代の競争優位性になります。
人間にしかできない直感と意味づけ: AIがどれだけ賢くなっても、なぜそれを作るのか?誰が幸せになるのか?という、プロダクトの本質的な問いに向き合い、その価値に「意味づけ」をするのは、私たち人間の役割です。この「意味づけ」ができる人は、AI時代においても、間違いなく最も価値の高い存在であり続けるでしょう。
挑戦と学びを促す文化、そして未来へのコミットメント
私たちは、この大きな変革を、全エンジニアと共に楽しみながら進めていきたいと考えています。「挑戦」と言うと成果へのプレッシャーや失敗への不安を感じるメンバーもいるかもしれません。また、日々の業務に追われ、新しい技術や働き方を学ぶ時間を日常の中に十分に取れていないエンジニアも多いでしょう。こうした心理的なハードルや時間的な制約は、私たちも認識しています。
しかし、このハードルを皆で共に乗り越えていきたい。「うまくいくか分からないけど、やってみたいこと」があるなら、その心の声に、耳を傾けてほしい。そして、その一歩を踏み出せる雰囲気は、自分から作っていくことができるはずで、その小さな「やってみたい」が、大きな挑戦のきっかけになるかもしれない。 私たちは、Sansan技術本部全体でAIを最大限に活用し、一人ひとりがこのAI時代の「非連続な成長」を牽引する未来のリーダーへと成長していくことを目指しています。Sansanはそのような成長を遂げるための投資を惜しみません。新しい技術を学ぶ機会、挑戦を後押しする文化、そして経験豊富なメンバーからのフィードバックを通じて、すべてのエンジニアのキャリアパスを全力でサポートしていきます。
この変革の先頭に立つ私自身が、挑戦と成長を全力で後押しします。一人ひとりの「挑戦」と「リーダーシップ」が、Sansanの未来を、そして社会を大きく変革していく原動力となるからです。
AI時代におけるエンジニアリングの新しい価値を創造し、共に次のステージへ進んでいける仲間を、Sansanは常に求めています。もしこのビジョンに共感し、共に挑戦したいと強く思うのであれば、ぜひ私たちのチームに加わってください。
Sansan技術本部ではカジュアル面談を実施しています
Sansan技術本部では中途の方向けにカジュアル面談を実施しています。Sansan技術本部での働き方、仕事の魅力について、現役エンジニアの視点からお話します。「実際に働く人の話を直接聞きたい」「どんな人が働いているのかを事前に知っておきたい」とお考えの方は、ぜひエントリーをご検討ください。