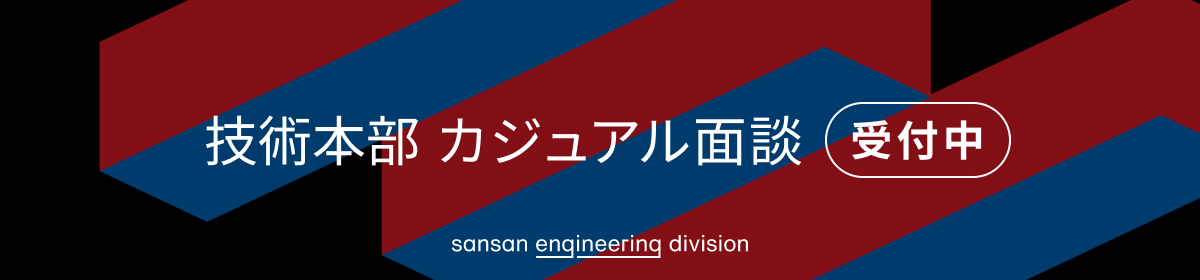この記事は、Bill One 開発 Unit ブログリレー2024の第14弾になります!

ぶっちゃけ、働くならBtoCとBtoBどっちがいいの?
就活や転職で仕事を探しているエンジニアの中で「BtoCプロダクトがいい」と仕事を探したことがある方はいますか?
何を隠そう、私も「BtoC以外考えない」という時期がありました。実際に、これまで5つのプロダクトで9年以上BtoC向けプロダクトのプロダクトマネジャーを経験してきました。そう、Sansanに入社するまでは。
こんにちは、Sansanのインボイス管理サービス「Bill One」で、受領領域のプロダクトマネジャーをしている森本です。2024年8月にSansanへ入社し、初めてBtoBプロダクトを担当することになりました。そんな私がBtoBプロダクトを担当し、BtoBとBtoCの開発における違いを知った上で、仕事探しにはそれらより重視すべきことがあると感じたため、仕事探しの知識として情報をシェアさせてください。
- なぜ転職先にBtoBプロダクトを開発する企業を選んだのか?
- BtoCとBtoBのプロダクトづくりを経験し、感じたこと
- 仕事探しは、BtoCかBtoBかより重視すべきことがある
- まとめ
- Sansan技術本部ではカジュアル面談を実施しています
なぜ転職先にBtoBプロダクトを開発する企業を選んだのか?
私の転職のきっかけは、キャリアの幅を広げるため、全く新しいことにチャレンジしたいと考え始めたことです。実は、転職活動を開始したときはBtoBプロダクトの開発に携わりたいとは思っていませんでした。そのため、BtoBプロダクト開発へのイメージも「プロダクトづくりはユーザーファーストでない」「営業の言いなりになる」など凝り固まったイメージを持っていました。
ただ考えてみると、BtoBであっても受注開発をしている会社とSaaSを提供している会社ではプロセスが違うことは容易に想像できます。SaaSは、一つのプロダクトを多くの企業で使ってもらえるようにする必要があるためです。当たり前ですが、そこの棲み分けさえも考えるフェーズに立っていませんでした。
過去に自分で選択肢を絞りすぎ、転職がうまくいかなかったこともあるため、今回は、自分で選択肢を絞りすぎず、カジュアル面談を受けていました。Sansanの担当者と会話を進めるにつれ、BtoB自体も新しいチャレンジであり、今後のキャリアを考えてもポジティブであり、経験してみたいという想いに変わりました。
BtoCとBtoBのプロダクトづくりを経験し、感じたこと
BtoBの開発に転向して半年が経過した今、感じていることを書いてみます。
ものづくりの根本は変わらない
基本的には、プロダクトは何かの課題を解決するものです。ユーザーに向き合い、ユーザーの課題を探索し、解決策を提案する。この観点は、BtoBであってもBtoCであっても変わりません。BtoBがユーザーファーストではないということは全くありません。
また、開発組織もアジャイルであり、開発の進め方についてもBtoBであれ、BtoCであれ変わらないです。
営業のパワーは想像以上にすごかった
入社前から、営業は強いだろうと思っていました。そのパワーは、私がイメージしていたよりずっと強かったです。だからこそ、業界で最も選ばれる請求書受領サービスになっていると感じました。良いプロダクトを作ったとしても、知られていなければ使われません。開発と営業の連携があるからこそ、現在のBill Oneがあります。
もちろん、営業が強いからこそ、営業の状態がプライオリティーや意思決定に大きく関わります。BtoCプロダクトを担当していたとき、営業の意見が反映されることはあまりありませんでした。それは、私が担当していたのはメディアであり、ユーザーに売る商品ではなく、広告で利益を得ていたためです。
BtoCであっても、事業フェーズ、事業内容、事業規模によって営業との密接度は変わってきます。そのため、BtoBとBtoCでの違いとしては切り分けられません。ただ、BtoBの方が営業と密接になる可能性は高いです。
ユーザー解像度の高いCSとプロダクトづくり
BtoCプロダクトを担当していた頃は、CSが集めたフィードバックはクリティカルなエラーを発見する場として活用していました。ただ、全てがデータ化されていたため、不具合は数字から発見できており、エラーの発見自体も年に数回程度でした。ユーザーのインサイトを調査する場合は、プロダクト開発側でアンケート調査やユーザーインタビューを実施していたため、その役割をCSに依頼することもありませんでした。
反対に、Bill OneではCS無しではプロダクトづくりが進みません。CSはお客様と密に話しているため、企業様の状態を把握しており、各社で異なる業務内容やフローをよく理解しています。プロダクトを改善する際にCSにヒアリングをしたり、リリース前の確認をしてもらったり、CSがいることでプロダクトづくりを円滑に進めることができています。
難易度の高いドメインにコミットが必要
全てのプロダクトでドメイン知識は必要です。ただ、ドメイン知識の難易度には大きな差があると思います。一般的に、BtoCプロダクトより、BtoBプロダクトの方が難易度が高いケースが多いです。一般の人が使わない機能は専門的であり、複雑な機能提供が必要になるからです。
私が現在担当するBill One の請求書受領サービスの、最大の利用者は経理担当者です。経理担当者の課題を見つけるには、まず、どんな仕事をしているのかから学ぶ必要がありました。入社前は、請求書を管理する人たちというイメージでしたが、請求書の管理は業務の一部であり、会社のお金の動きを管理し、記録を残し、財務状況を分析し、報告する人たちであることを知りました。また、法律での規制もあり、これらを学ぶことは難易度が高いです。入社して半年ですが、まだ理解できていない点は多いです。
自分から課題を発見し、どのように解決するべきかを見定めるにはドメイン知識の獲得は必須です。今は、CS、セールス、法務、先輩PdMのみなさんがいてくれるため、プロダクト改善についていけています。転職する際は、自分がコミットしたいと思えるドメインを見つけることも大切です。私自身、Bill Oneでは、会社でのお金の動きが学べると思い、それも魅力的だと思っていました。
利用者と決裁者が異なることで優先度が変わる
BtoCプロダクトでは、ユーザー自身が利用から決済までを自己完結できます(キッズ向けプロダクトなど例外もあります)。一方で、BtoBプロダクトでは組織が利用可否を判断し、その組織に所属する人たちが利用をします。そのため、決裁者と利用者が同一ではないということが起きます。これが、BtoBプロダクトが難しいと感じる点です。
ユーザーファーストで体験を良くしたとしても、決裁者が持っている課題が同じではない場合、プロダクトを選んでもらえることはないのです。だからこそ、選んでもらえる魅力的な機能開発は必要ですし、優先度が高まります。利用者が喜ぶような機能開発と決裁者が喜ぶような機能開発が同じである場合は問題ないのですが、開発コストに上限があるので、どちらかを選ばなければいけないことは発生します。
仕事探しは、BtoCかBtoBかより重視すべきことがある
実際にBtoCからBtoBに転職したことにより感じたことを記載しました。事業内容、事業規模、フェーズ、プロダクトにおける開発の立ち位置が違うだけで、ものづくりで重視すべき点が変わってきます。
BtoCであっても、営業が強い会社もあれば、CSがプロダクトに密に関わる会社もあります。また、プロダクトマーケットフィット前のプロダクトでは、BtoBであれBtoCであれ、スピーディーな開発とリリースを重ね、確度を高めていく必要があります。成熟した大規模プロダクトでは安定性が必要であり、初期に作ってきたコードや体制を整理し、よりシンプルに誰でも開発ができることが求められます。
今回の転職活動から、BtoCかBtoBかで仕事を決めることは正しい選択の絞り方ではないという考えに切り替わっています。重視すべきは、事業内容、事業規模、フェーズ、プロダクトにおける開発の立ち位置です。これまでは「BtoCがよい」という理由から、無意味に選択肢を狭めてしまっていたのです。
まとめ
私の経験からBtoCかBtoBの違い、仕事探しで何を配慮すべきかを紹介しました。これは、私の事例であり、皆さんに当てはまらないかもしれないです。
また、多くのプロダクトでは、機能が複数あるケースが多いです。Bill Oneも同様で、受領だけではなく、発行や経費精算の機能があります。いずれも、事業内容、事業規模、フェーズが異なっています。Bill Oneは該当しませんが、プロダクトをBtoCとBtoBの双方に提供していることもあり、一つの会社に入っても選択肢は色々あるはずです。
転職活動をしているときに、担当したいプロダクトを具体的にイメージし、そのプロダクトに携われるかを確認することも大切です。事業内容、事業規模、フェーズでプロダクトを選んでも、全く別のプロダクトに配属されては意味がなくなります。希望が通るように、面接で「なぜ自分がそのプロダクトを担当すべきなのか」を説得できる事前の準備はしっかりしてくださいね。
自分がやりたいことに一番フィットする仕事はなにか?という考えを持ち、仕事探しができるといいですね。Good Luck!
* ブログリレーの最新の投稿についてはXアカウント @SansanTech でお知らせしますので、フォローよろしくお願い致します。
Sansan技術本部ではカジュアル面談を実施しています
Sansan技術本部では中途・新卒採用向けにカジュアル面談を実施しています。Sansan技術本部での働き方、仕事の魅力について、現役エンジニアの視点からお話します。「実際に働く人の話を直接聞きたい」「どんな人が働いているのかを事前に知っておきたい」とお考えの方は、ぜひエントリーをご検討ください。